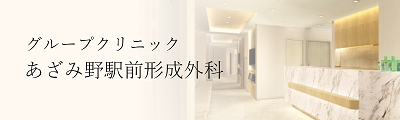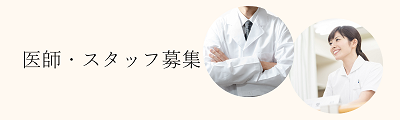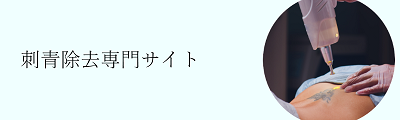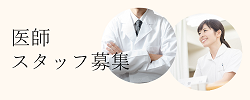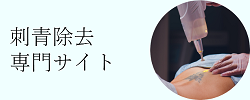センター南形成外科皮フ科では、患者さんにその時点での最適な治療をワンストップで施せるよう、皮膚科と形成外科の認定専門医が揃っています。
少しでも気になることがありましたら、当院にお気軽にご相談・ご来院ください。
皮膚のかゆみや痛みのトラブル
かぶれ(接触性蕁麻疹)
症状
皮膚に直接触れたものが原因となって起こる炎症や湿疹を接触性蕁麻疹(かぶれ)といいます。
初回接触でも、誰にでも発症しうる一次刺激性と、繰り返し接触することによって発症するアレルギー性のものがあります。
原因として化粧品、草木、毛染め、洗剤、湿布、金属などがあります。
治療
原因物質を探して、その物質が含まれるものに接触しないように注意します。
ステロイド外用薬や、内服薬を用いて治療します。
虫刺され
症状
虫に刺された直後からその部位が赤く腫れたり、症状が強いと水ぶくれになったりシコリになったりします。
小さいお子さんは抗体がまだ無いため、特に腫れやすいです。
メモ
掻き壊すと、とびひ(伝染性膿痂疹)や治りにくい痒疹(硬くシコリのある湿疹)となり、長期化することもあるので、皮膚科へ早めの受診をお勧めします。
乾燥肌(皮脂欠乏症)
症状
皮膚の脂が減少することで皮膚の水分量が減り、皮膚が乾燥した状態になることです。
外気が乾燥する秋から冬にかけて発症することが多く、中高年の下腿や腰背部によく見られます。
表皮バリア機能が低下し、次第に痒みをともなってひび割れたり、赤みも生じてきます。(皮脂欠乏性湿疹)
治療
保湿剤を外用して、湿疹にはステロイド外用剤で治療します。
じんましん
症状
蚊に刺されたような、やや盛り上がった痒みの強い発疹が、数時間から24時間以内に出没を繰り返す皮膚疾患をじんましんといいます。
1~2週で治っていく急性じんましんと、1ヶ月から数年にわたって発症する慢性じんましんがあります。
じんましんの原因は食べ物や薬、感染症やストレスなど様々ですが、慢性じんましんでは原因を特定することは困難です。
治療
原因があれば除去をし、抗ヒスタミン剤の内服が主体となります。
薬を内服すれば急性じんましんの場合、1−2週で症状が治まりますが、慢性じんましんの場合数週間から数ヶ月かかることもあります。
中止するとまた出ることが多いので、医師の指示通りに徐々に減らしていきます。
アトピー性皮膚炎
症状
アトピー性皮膚炎とは強い痒みと治りにくい湿疹という特徴を持つ、アレルギーに関連した疾患です。
アトピー性皮膚炎は遺伝的な体質に後天的な環境要因が刺激となって発症すると考えられています。
多くの患者さんは遺伝的素因(アトピー素因)として、アレルギーを起こしやすい体質と、皮膚が乾燥しやすい素因(ドライスキン)を併せ持っています。
治療
① 原因・悪化因子の検索と対策
② スキンケア
③ 薬物療法(塗り薬・飲み薬)
メモ
治療の3本柱を基本に、症状を和らげ、対症的に軽く経過する状態を維持することを目標とします。
ケロイド
症状
傷が盛り上がるように治ったもので、赤み、痛みや痒みを伴うことが多いです。
本来の傷の範囲を超えて正常皮膚まで病変が広がります。
徐々に増大し、ある時期に落ち着く場合と増大傾向を続けるケロイド(真性ケロイド)など程度は様々です。
治療
内服、ステロイドテープ、ステロイド注射、圧迫療法が基本です。
さらに腫瘍内切除というケロイドの範囲内での切除縫縮や、放射線治療の併用も選択していきます。
メモ
ケロイドは完全に治すことが期待できない場合が多く、再発や悪化も多いです。
しかし治療により症状軽減の期待はできます。
たこ・ウオノメ
症状
繰り返しの機械的刺激による角質の増殖で、形状により胼胝(たこ、べんち)や鶏眼(けいがん、ウオノメ)と呼んでいます。変形や圧迫による痛みを伴います。
治療
コーンカッターで角質を削ります。ウオノメでは芯をくり抜くこともあります。
症状によっては凍結療法や角質を柔らかくする貼り薬や塗り薬を使っていきます。
メモ
適切な処置をしないと症状がひどくなる傾向があります。
たこだと思っていたものが実はウィルス性のイボということもありますので、早めの受診をお勧めします。
皮膚潰瘍・褥瘡
症状
皮膚や皮下組織の構造が破綻し、いつまでも傷が改善しない状態です。
血流障害によるところが多く、その原因として基礎疾患(糖尿病、下腿静脈瘤など)や感染、持続する圧迫(褥瘡・床ずれ)などがあげられます。
他にも、放射線治療後の難治性潰瘍、皮膚の病気に伴う皮膚潰瘍、熱傷後の組織ダメージによる治癒遅延など、傷を治すための土台の不具合が本質的な問題ということもあります。
治療
まずは基礎疾患や感染の治療、除圧など原因の改善を考えます。同時にデブリードマン(不良組織の排除)、特殊な外用薬を使うなどして創面を新鮮化させ、創傷治癒を促していきます。
最終的に治りが悪い場合は傷を縫い縮めますが、安易に状態の悪い皮膚組織を寄せてもつかないことが多いです。時には傷の状態を見きわめて、無傷な組織で傷を覆う植皮術や皮弁形成術といった方法を選択することもあります。
メモ
傷がなかなか治らないと、骨髄炎、指の切断、全身状態の悪化につながることもあります。
また時間をかけてやっと治ったような傷痕は、本来の皮膚の柔軟さは期待できず、様々な不都合をもたらします。
予防には早めの適切な処置が重要です。
霰粒腫・麦粒腫
症状
霰粒腫(さんりゅうしゅ)とは、まぶたにあるマイボーム腺に肉芽腫ができてしまった病気です。無菌性の炎症が原因で、痛みを伴わないまぶたの腫れが一般的です。
同じ様にまぶたが腫れる病気として、麦粒腫(ばくりゅうしゅ、ものもらい)がありますが、こちらはまぶたにある分泌腺への細菌感染が原因で、痛みを伴うことが多いです。
治療
霰粒腫ではステロイドを注射したり、原因の肉芽腫を摘出したりして治していきます。
大きく腫れているものや炎症を繰り返すものなどは、肉芽腫が瞼板(硬い結合組織でまぶたのフレームの役割)に入り込むように存在することが多く、瞼板を一部含むように切除しなければ治りません。
小さくくり抜くように取りますので、まぶたが変形することはありません。
麦粒腫では抗生剤を含む点眼、内服を続けます。大きなものでは切開排膿することで感染巣をきれいにすることがあります。
メモ
霰粒腫はマイボーム腺の詰まりが原因で、ホルモンバランスの乱れで分泌物がうまく排出されない、化粧品などが詰まってしまうことなどがその要因と言われています。
麦粒腫は感染が原因のため、汚れた手で目をこすらない、コンタクトレンズの使用の際は、衛生管理を徹底することが予防につながります。
皮膚の感染によるトラブル
にきび(尋常性ざ瘡)
症状
にきびは主に若い人の顔面、胸部、背部に多発する毛包一致性の面ぽう、丘疹、膿疱で、皮脂の分泌亢進と毛穴のつまりが原因で生じます。
皮脂分泌の亢進はホルモンバランスの乱れ、食事、睡眠不足、ストレスなどで生じ、毛穴のつまりは、化粧や紫外線などの外的刺激が原因となります。
治療
毛穴のつまりを取る外用剤(アダパレンや過酸化ベンゾイル)を主に使用し、必要に応じて抗生剤の外用や内服を行います。
肌のターンオーバーを整えるのに3ヶ月くらい治療を継続することが大切です。
メモ
保険治療で良くならなければ、ピーリングも行なっていますのでご相談ください。
水虫(白癬)
症状
水虫は白癬菌というカビによる感染症の一種です。
足の裏の皮がむけたり、カサカサしたり、足の指の間がじくじくして皮がむけたりします。
痒みのある水疱を生じることもありますが、無症状のこともあり、放置して悪化してしまう場合もあります。
水虫の菌が爪にまでうつってしまうと、爪が白く濁ったり厚くなってきます。
治療
抗真菌剤の外用剤や内服薬を使います。外用は足裏全体に広めに塗ります。
症状がなくなってすぐ外用を中止すると再発するので、1−2ヶ月は続けて外用してください。
爪の水虫で外用剤で効果が出にくい場合は、内服薬を用いることもあります。
最低半年は内服継続が必要で、定期的に血液検査も必要になります。
口唇ヘルペス
症状
口唇ヘルペスは単純ヘルペスウィルスに感染することで起こる病気です。
唇やその周りにピリピリするような痛みが生じ、軽い痛みを伴う赤い水ぶくれができます。
ヘルペスウィルスは一度感染すると神経に潜伏しており、発熱、ストレス、疲労や強い紫外線などで免疫が低下すると、ウィルスが活動して症状が出てきます。
治療
抗ヘルペスウィルス薬の飲み薬や塗り薬を用います。
帯状疱疹
症状
帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウィルスの感染によって発症します。
初めてこのウィルスに感染した時には、水ぼうそうとして発症します。
水ぼうそうが治った後も、ウィルスは体内の神経節に潜んでいます。
ストレスや過労などで免疫力が低下すると、潜んでいたウィルスは活動を始め、神経を伝わって皮膚に帯状に発症します。
ピリピリと刺すような痛みと、これに続いて赤い斑点と小さな水ぶくれが帯状に現れます。
治療
抗ウィルス薬を1週間続けて服用します。
メモ
できるだけ早く皮膚科を受診して発病早期に適切な治療を行うことで、症状を軽くし、合併症や後遺症である帯状疱疹後神経痛のリスクを減らすことができます。
いぼ(尋常性疣贅)
症状
「いぼ」はヒト乳頭腫ウィルスというウィルスの感染症で、主に手・足の指や足の裏にできます。
時間が経つにつれ大きくなったり、周囲や他の部位にうつって行きますので、早めに治療を受けてください。
治療
液体窒素で冷凍凝固を行います。一度の治療では治癒は難しく、1−2週に一度のペースで通院する必要があります。
メモ
足の裏のイボをウオノメやタコと思って気づかないことがありますが、子供の場合ウオノメやタコはまず出来ないので、皮膚科専門医にご相談ください。
水いぼ(伝染性軟属腫)
症状
水いぼは、正式には伝染性軟属腫(なんぞくしゅ)といい、軟属腫ウィルスの感染症です。
乾燥肌やアトピー性皮膚炎のある患者さんに多く見受けられます。
乾燥肌やアトピー性皮膚炎があると皮膚のバリア機能が低下するため、細かいキズからウィルスが入りやすいことと、痒みで引っ掻くことによりうつしてしまうことが多いのです。
肌の弱いお子さんは保湿剤でしっかり保湿することが大切です。
治療
無治療でも免疫ができると半年ほどで自然軽快することもありますが、幼稚園や保育園から除去してくださいと言われることがあります。
除去する場合はピンセットで1つずつつまみ、内容物を出す方法が一般的です。
強い痛みを伴うので、当院では麻酔テープを用いて除去しています。
とびひ
症状
「とびひ」は正式には伝染性膿痂疹(のうかしん)といい、主に黄色ブドウ球菌による皮膚の感染症です。
ジクジクした紅斑や水ぶくれができ、放っておくと次々と他の部位に伝染します。
治療
抗生剤を内服し、患部はシャワーでよく洗ってから抗生剤の軟膏を外用してガーゼで覆います。
メモ
虫刺されやあせも、湿疹を掻き壊すことでとびひになりやすいので、早めに皮膚科で治療を受けることが大切です。
癜風(くろなまず)
症状
癜風菌というカビが皮膚表面に付着している状態です。
「くろなまず」とも呼ばれ、しみのような境界のはっきりした黒い色素斑としてみられます。
また同じ癜風菌でも、白色癜風という白い脱色斑としてみられたりすることもあります。
汗をかきやすく皮脂分泌の多い胸や背中、わきなどの皮膚にできやすいです。
特に夏場の発症が多い傾向にあります。
治療
抗真菌薬を塗ることで改善していきます。
メモ
真菌による皮膚症状は、抗真菌薬を続けることで軽快しますが、治ったと思っても菌は多少なり残っているため、さらに1ヶ月ぐらいは続けることが大事です。
それでも癜風はまた夏場に再発することが珍しくありません。
皮膚の形態(形や見ため)のトラブル
母斑・あざ
症状
ほくろ、茶あざ、赤あざなど皮膚の色のトラブルです。
その中でも著しく不利益をもたらす見た目を呈するものや、皮膚癌を疑うようなものが保険治療の対象となります。
視診でわかるものもが多いですが、良悪性の判断がつかないものもあり、そのような場合は積極的な治療や検査をお勧めしています。
治療
視診、問診、ダーマスコープなどでどのような疾患かを判断していきます。ほくろでは治療と病理検査を兼ねて手術を行なう方が多いです。
メモ
蒙古斑、サーモンパッチ、いちご状血管腫など幼少期にあったものが自然消退する傾向のあるものもありますので、ぜひ専門家の診察を受けてみて下さい。
できもの(粉瘤・脂肪腫など)
症状
皮膚または皮膚の下にあるもので、医学的に本来なくてもいいもの、あってはいけないものが治療対象です。
代表的なものとして以下のようなものがあります。
① 小さい頃からあるもの・・・あざ、血管腫、副耳、耳瘻孔、など。
② 後からできたもの ・・・ほくろ、いぼ、粉瘤、脂肪腫、繊維腫、石灰化上皮腫、毛巣洞、ガングリオン、など。
通常は特に症状がなく、見た目の問題だけです。しかしどんどん大きくなっていくもの、いずれ感染を効率に起こすようなものも多くあります。悪性化する傾向にあるもの(前癌病変)や悪性腫瘍そのものの可能性もあります。そのためこのような疾患は積極的な治療・検査をお勧めしています。
治療
手術による切除摘出を行います。
このようなできものは、ほとんどが物理的に除去しなければ治りません。
また取ったもの(検体)を病理検査することによって初めて良性か悪性か、取りきれているのか、取り残しがあるのかが確定するからです。
メモ
色素性病変では、デルマスコープという皮膚を拡大視する機械を使って診断の補助に役立てていますが、最終的な確定診断は病理検査の結果です。
なお、当院では当日の手術希望の方も対応しています。
皮膚癌
症状
皮膚にできた悪性腫瘍を皮膚癌と呼んでいます。
悪性黒色腫、有棘細胞癌、基底細胞癌などが有名ですが、他にもボーエン癌や日光角化症などがあります。
パジェット病、白板症、脂腺母斑といった、いずれ悪性化する可能性のある皮膚病変(前癌病変)もあり、積極的な検査、治療が必要です。
治療
明らかな癌の場合や検査の結果皮膚癌とわかった場合は、大学病院などに紹介させていただいています。
前癌病変や皮膚癌が疑わられるようなものは、生検や手術による切除を行い、病理検査をすることで確定診断をつけていきます。
メモ
診断や進行状況を見極めて、規約に沿った方法で腫瘍やその周囲の完全切除を行っていきます。
転移のリスクをさげるということでは、早期発見が大事ですが、次に大事なことは、手を加えてからこの完全切除までの時間が短いことです。
そのため皮膚癌がわかった時点で、一連の治療をスムーズに行なうことができる高度医療機関を紹介しています。
外傷(けが)
症状
切り傷やすり傷、犬に噛まれた(犬咬傷)、とげや木片が刺さったといった外傷です。
骨折や神経損傷の有無などは初期治療では重要な判断材料です。
治療
必要に応じて局所麻酔、傷の洗浄、テープ固定、縫合、軟膏処置などを行います。
骨折や神経損傷などが疑われる場合は、専門病院に紹介することもあります。
メモ
適切な初期治療をしないと、治りが悪かったり、外傷性タトゥーや肥厚性瘢痕といった目立つ傷跡になったりと、あとあとに影響する可能性があります。
熱傷(やけど)
症状
皮膚がヒリヒリした痛み程度から、水泡、皮膚のただれなど症状は程度によって様々です。
湯たんぽなどによる低温熱傷は、時間が経ってから重度熱傷(3度熱傷)だったことが判明することもあります。
治療
初期治療はクーリングと軟膏処置です。
その後炎症が落ち着いてきたら特殊な創傷被覆材を使ったり、軟膏を変えるなどして上皮化を促します。
皮膚欠損の状態では縫縮や植皮を行うこともあります。
メモ
やけどだと思ったら、まず保冷剤や直接の水道水などで患部を十分冷やしてください。
冷やすことで痛みの緩和と同時に、熱傷範囲を最小限にすることができます。
爪
症状
巻き爪、爪の剥離、爪が分かれて生えてくる副爪、爪周囲炎、グロムス腫瘍などです。
痛みや靴下がひっかかるといた不都合が伴います。
治療
症状に応じて 爪きりの指導、テーピング療法、陥入爪手術や爪母除去術を行ないます。
巻き爪ではワイヤー矯正による治療も行っています。
メモ
爪の異常では、爪の栄養状態、感染、乾燥などが原因の事があり、複合的な判断・治療が必要な場合もあります。
副耳・耳瘻孔
症状
副耳(ふくじ)とは、耳前部や頬に生まれつきみられる小さな突起物で、中に軟骨を含むことが多く、副耳と耳の軟骨同士がつながっていることもあります。
片側に一個だけのことが多いですが、複数あったり、両側に見られたりすることもあります。
耳瘻孔(じろうこう)とは、生まれつき耳介や耳前部に小さな穴があり、管状または袋状に奧へと耳介軟骨まで続く皮膚のトンネルのようなものです。
トラブルを起こすことがなければそのまま様子を見てもいいのですが、この穴は不衛生になりがちなため、細菌の巣になりやすく、感染を繰り返すこともあります。
副耳と耳瘻孔は、どちらも耳では頻度の高い疾患の一つです。
治療
副耳の中にある軟骨を深くまで取るように切除をすることできれいに治ります。
耳瘻孔は上皮成分の取り残しのないように袋ごと全摘していきます。
メモ
診察や抗生剤投与のみでしたら年齢を問いません。
手術治療では、局所麻酔下に行いますので、当院では中学生以上を対象としています。
毛巣洞
症状
お尻にできる毛巣洞は皮膚に生じる小さな穴で、中に毛を含んでいます。
体毛が皮膚に刺入することがきっかけで、長時間座りっぱなしの仕事や体毛が濃いなどがリスクとして考えられています。
その後はどんどん皮膚のトンネルが奥へと拡がります。皮膚がこすれあうワキなどでも見られます。
普段は無症状ですが、感染が起こると痛みや腫れ、膿が出てきたりします。
治療
感染が起きているようでしたら、皮膚切開をして創部をきれいにしたり抗生剤で様子をみます。しかし根本的に治すには、できてしまった皮膚のトンネル(毛巣洞)を全て切除摘出する必要があります。
メモ
長時間座っている生活や体毛が濃いなど、条件が変わらないと再発する可能性がありますので、日常生活の工夫、お尻(特に左右の皮膚がこすれる部分)の永久脱毛などで予防していきます。
薄毛・脱毛症
お薄毛の種類として 男性型脱毛症(AGA)、円形脱毛症、瘢痕性脱毛症(やけどあとや手術の傷あと)があげられます。
治療
保険による治療と自費診療があります。
それぞれ一長一短あり、また原因によって治療法が異なりますので、症状を見た上で治療法を決めるようにしています。
保険…ステロイド外用、凍結療法、禿髪部の縫縮、皮弁形成
自費…内服(フィナステリド、パントガール)、ハーグ療法、植毛
メモ
薄毛の程度が改善するという、期待の持てる治療ではあります。
しかし、治療方法によっては、すぐに効果が出るのではなく、数ヶ月単位で出てくることがあり、継続して治療を行うことが大事です。
また生活習慣が影響していることもあり、日常生活の改善が必要になることもあります。
皮膚の機能的なトラブル
眼瞼下垂症
症状
まぶたを無理なく挙げたときに、十分に目が開かない状態のことです。
明確な数値化された基準はありませんが、当院では眉毛を押さえて、まぶたの力だけで目を開けたときに、黒目の見え方が6割以下なら治療の適応と考えています。
眼瞼挙筋が縮むことで、腱膜(挙筋と瞼板を連結)、瞼板(まぶたのフレームの役割)が連動して目が開きます。
この腱膜が加齢や長年のコンタクトレンズの脱着などの刺激でたるんでくると、筋肉の力が効果的に瞼板に伝わらず、まぶたが開けづらくなります。
このため眠そうな目を呈したり、よりよく見ようと眉毛を過剰に挙げたり、顔をあげて下目遣いをするなどして、頭痛や肩こりの原因になることもあります。
治療
⑴ まぶたを押し下げている皮膚を適当量切除することで、開けやすくなります。
⑵ 腱膜を露出することで、滑りが良くなり開けやすくなります。
⑶ 腱膜の長さを縮めることで、挙筋の動きが効果的に伝わりやすくなります。
以上を一度の手術で行っていきます。
メモ
治療の目的は、視野が良くなることです。また目元がスッキリすることで若々しくなる、姿勢も良くなり頭痛や肩こりがなくなるといったことも期待できる治療です。
逆さまつ毛
症状
まつ毛がチクチク目にあたる症状で、放置していると、角膜に傷をつけるといったニ次的な問題が起こります。
原因は大きく2つに分けられます。
① 睫毛内反(しょうもうないはん)は、まつ毛全体が内向きに生えそろったもので、ほとんどの逆さまつげがこのパターンです。多くは内側〜中央のまつ毛が目にあたり痛みをもたらします。
上下両方のまつ毛が内反しているもの、ポッチャリした子供の頃にあった症状が大人になったら軽快するなど、程度は様々です。
② 睫毛乱生(しょうもうらんせい)は、数本のまつ毛が列を乱して生えることで、これらが眼球に触れてチクチクした症状を出します。
これらは①②の症状は、上下のまつ毛それぞれに起こりうることで、同時に両方が見られることもあります。
治療
睫毛内反では、手術が選ばれます。
根本治療では、まつ毛の生えている皮膚とその下の皮下組織の位置関係を少しずらし、生える向きを変えていきます。上まぶたに限り、糸で二重を作ることで、まつ毛の生える向きを変える方法があります。
睫毛乱生では、その原因のまつ毛を1本1本電気凝固よる永久脱毛をすることで改善させていきます。
メモ
痛み緩和のため、まつ毛パーマやまつ毛を抜いている方が多いのですが、症状の程度がわかるように、診察時にはビューラーなども含めたまつ毛矯正をしていない自然体の状態でいらしてください。
瘢痕拘縮
症状
皮膚が足りない、皮膚自体の柔軟性がないなどによるつっぱり・ひきつれ(瘢痕拘縮)、皮膚とその下の筋膜や骨膜との癒着による皮膚の可動制限など、傷が治った後に起こる不都合です。
治療
主にZ形成術、W形成術、皮弁形成や植皮術など、形成テクニックを使って治していきます。また傷を柔らかくする薬を使い症状の改善を行う事もあります。
メモ
動きに支障がある場合や、動かすことで痛みが伴うようなときに保険治療の適応となります。
見た目のみの傷跡修正は自費診療となります。
腋臭症・多汗症
症状
腋臭症とはワキガとも呼ばれ、ワキから特異な臭い(ワキガ臭)がする状態です。
アポクリン汗腺と呼ばれる汗を出す器官の分泌亢進が原因で、この腺は耳の中、乳輪、外陰部などにも分布し、同様の臭いがすることもあります。
診療をしていると、臭いがないのに自分がワキガだと思って来院する方がいらっしゃいます。
しかし、皮脂の臭いや黄菌毛と呼ばれる脇毛につく細菌が原因だったり、他人からの間違った指摘を疑わずにずっと悩んでいたり、思い込みによる自己臭恐怖症の可能性もあります。
治療の適応の有無など適切な見解をお伝えしていきますので、是非ご相談していただければと思います。
治療
手術によって臭いの元であるアポクリン汗腺をとっていく皮弁法(剪除法)を行います。
メモ
保険適応の手術では、大きな傷が残るということで敬遠している方も多いと思いますが、当院ではワキの中央に2センチほどの傷で済ませます。
これでも十分全体を見渡すようにアポクリン汗腺を取り除くことができます。
舌・上唇小体短縮
症状
舌小帯とは舌の裏側中央にある索状物、上唇小帯とは唇の真ん中と歯茎をつなぐ索状物です。
この小体が短いことで、舌を前方に伸ばすことができない、唇の動きが制限されてしまうなどの不都合が伴います。
治療
小帯を切離し、つっぱりを解除することで改善していきます。
メモ
当院では手術を局所麻酔で行うため、中学生以上が対象となります。
上唇小帯では、怪我をしたときに不全断裂の状態になり、切れた部分が不自然に残ったままの状態で、傷が治っている方も多いです。
陥没乳頭
症状
陥没乳頭(かんぼつにゅうとう)は、乳頭(乳首)が結合組織や不十分な皮膚の支持力により、奥に引き込まれた状態にあります。
指で簡単に出てくるものから、全く出てこない、乳頭トップが滑らかではなく二つに分かれたような形状など程度は様々です。
治療の趣旨としては、できるだけ正常な授乳ができることを想定していますので、乳頭の突出した形態の維持、乳管の温存が目的となります。
治療
軽度の陥没では、乳首のつけ根を軽く締め上げるような方法で、突出を促します。
中~重度では中の結合組織に手を加えることで、強固な引き込みを解除していきます。
メモ
正常な授乳ができない、またはできないことが予想される場合は、保険適応による治療の対象です。整容面のみの問題では自費診療になります。
副乳
症状
本来の乳房とは別に見られる乳房を副乳と呼びます。
ただ実際は小さなしこり程度がほとんどで、大きくふくらんだ乳房というわけではありません。
ワキから乳頭、太ももの内側を結ぶミルクラインと呼ばれる弓なりの線上にでき、成長に伴い副乳も発育してきたり、生理時に腫れや痛みを伴ったりします。
治療
乳腺を含んだ副乳組織を取り除き治していきます。
メモ
男性1.5%女性5%で出現するとの統計があり、稀ですが男性でも見られる疾患ではあります。
男性器
症状と治療
包皮炎…陰茎皮膚や亀頭表面がただれやひび割れを起こし、いつもジクジクしていて、しみるような痛みがある状態です。
軟膏で経過をみていきますが、皮膚のあまり具合など、環境が変わらないと改善が見込めない場合は手術をしていきます。
真性包茎…包皮の開口部が狭く、亀頭が露出しない状態です。
カントン包茎では、無理に剥くと露出はするがその後包皮が戻らなくなることがあり、注意が必要です。
包皮環状切開で過剰な包皮を切除し、正常な見た目に近づけていきます。
包皮癒着…包皮と亀頭が接する面が一体化してしまい、包皮が剥けない状態です。
全体が癒着していることもありますが、多くは亀頭上面の一部がついている程度です。
局麻下に丁寧に剥がしていきます。
メモ
保険治療では、機能的障害を伴うものが治療対象のため、真性包茎またはこれに準ずるものに限られます。仮性包茎、フォアダイス(白いブツブツ)などの治療は保険対象外のため、自費診療による治療を当院では行っています。